
Land&rutoオリジナルコラム
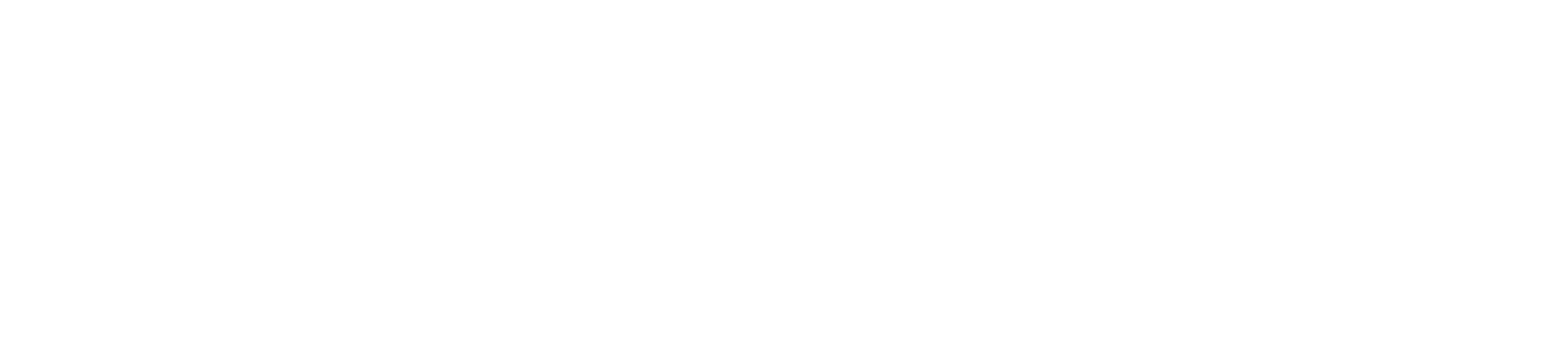

北上 寿一
Land&ruto店長
メーカーによって使用しているレンズ素材や偏光フィルターの種類、製法には大きな違いがあり、価格や耐久性、見え心地にも差が生じます。




カラーレンズのメリットとデメリット

メガネのカラーレンズの効果 カラーレンズは色で印…

偏光レンズのデメリットとは?偏光レンズのメリット…

偏光レンズの見分け方 簡単に見分ける方法

偏光レンズと調光レンズの違いと購入時の見分け方

偏光レンズで運転するのは危険なのか?夜間時の注意…

調光レンズのデメリット 色が変わるレンズのメリッ…
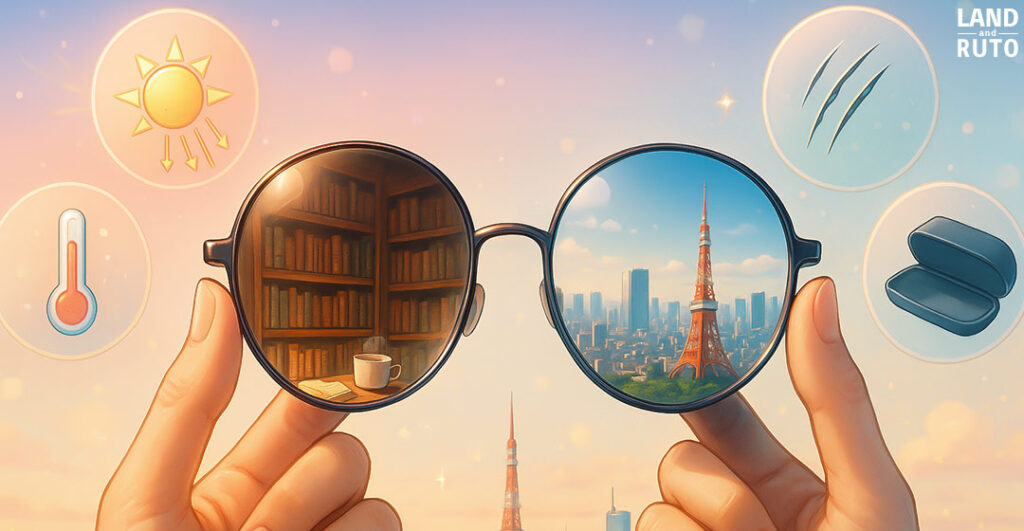
調光レンズの寿命はどれくらい?寿命を延ばす使い方
偏光レンズメーカーを比較
各メーカーの違いと選び方
偏光レンズメーカーの違いと特徴
Kodak LENS コダック
コダックの偏光レンズは、業界内で非常に高い評価を得ているものの、一般のユーザーにはあまり知られていません。
その理由は、コダックが主に業界関係者や専門家向けのパンフレットやホームページで情報を提供しているため、一般の目に触れる機会が少ないからです。
中でも「PolaMAX Pro」という製品は、偏光レンズ市場でトップクラスの性能を誇ることで知られています。
このレンズにはコダックの最先端技術や専門的なノウハウが詰め込まれており、高い品質と優れた性能を兼ね備えています。
PolaMAX Proには以下の3つの主な特徴があります。
- ネオコントラスト機能
景色や物体のコントラストが強調され、細かな部分まで鮮明に見えやすくなります。これにより、より鮮明な視界が得られます。 - UV420カット
有害な紫外線を効果的にカットし、目の健康を守りながらクリアな視界を提供します。 - 視界の明るさ
独自の技術により視界を明るくすることで、薄暗い場所でもはっきりと見えるように工夫されています。
これらの特性により、PolaMAX Proはスポーツやアウトドア活動を楽しむ人々に特におすすめの偏光レンズとなっています。
HOYA(ホヤ)
HOYAは日本を代表するメガネ用レンズのトップメーカーです。
同社が持つ独自の技術の一つに、「コーティングで偏光機能を持たせる」という方法があります。
この技術を採用した製品が「HOYA(ホヤ)ポラテック」です。
従来の偏光レンズは、レンズの間に偏光フィルムを挟む方法が一般的でしたが、HOYAポラテックではレンズ表面に直接偏光膜をコーティングしています。
この新しいコーティング方式により、フィルムを挟む構造で起こりがちな剥離リスクが大幅に軽減されました。
接着剤を使用しないため、接着剤の剥離によるトラブルの心配もありません。
この技術によるメリットは、レンズの厚みを抑えられることです。
特に強度近視でレンズが厚くなりやすい方には、薄型化できるという大きな利点があります。
ナイロールやツーポイントなど、さまざまな形状のフレームにも対応可能で、フレーム選択の幅が広がります。
耐久性に優れている点も特徴の一つです。
ただし、いくつか注意点もあります。
レンズ表面のコーティングが偏光機能を担っているため、傷がつくと偏光機能が低下する可能性があります。
薄いカラーのレンズの種類が少ないことや、薬品などが付着するとコーティングが変質するリスクがあることにも注意が必要です。
さらに、度なしの場合でも価格がやや割高に感じられるかもしれません。
これらのメリットと注意点を理解したうえで、HOYAポラテックを検討すると良いでしょう。
OAKLEY(オークリー)
オークリー(OAKLEY)は、最先端の「HDPolarizedテクノロジー」を採用した単層レンズを提供していることで知られています。
この技術は、接着剤やフィルムを一切使わず、レンズの成型と同時に偏光膜を組み込むという革新的な製造方法です。
従来の偏光レンズでは接着剤が使われることが多くありましたが、この新技術により高い透明度と歪みの少ない視界が実現されています。
オークリーのレンズはミラーのバリエーションが豊富で、素材として「Plutonite®(プルトナイト)」という特許取得済みの特殊素材を使用しているのも特徴です。
この素材は非常に丈夫で割れにくく、耐久性に優れているため長期間の使用にも適しています。
さらに、オークリー独自の特許技術である「PRIZM(プリズム)偏光レンズ」は、偏光効果と同時にコントラストを高めることで、より鮮明でクリアな視界を提供します。
ただし、このPRIZM偏光レンズはオークリー専用のフレームにのみ対応しており、他社のフレームには使用できません。
オークリーの偏光レンズは薄めのカラーのバリエーションがないため、一部のユーザーにとってはデメリットに感じられるかもしれませんが、これらの革新的な特長が高く評価され、多くのファッション愛好者やスポーツ愛好者から支持されています。
TALEX(タレックス)
TALEX(タレックス)は、日本の偏光レンズ市場をリードするブランドとして、多くのユーザーから高い支持を得ています。
その人気の理由は、ユーザーのニーズを深く理解し、用途に合わせて濃い色から薄い色まで幅広いカラーラインナップを提供していることにあります。
特に、ルアーフィッシングを楽しむ人々の間ではよく知られた存在です。
タレックスのレンズは、偏光フィルターをレンズ内部に挟み込む「サンドイッチ構造」を採用しています。
高い接着技術により透明度や歪みといった課題を克服し、非常にクリアな視界を実現しました。
雑光を効果的にカットしながらも明るさを損なわないため、視認性の良さが多くのユーザーから評価されています。
一方で、度付きレンズを選ぶ際には注意が必要です。
サンドイッチ構造の特性上、通常よりレンズが厚くなる傾向があります。
タレックスの製品は、40年以上培った技術力を背景に、製造工程の60%以上を手作業で行っています。
その高い品質と完成度は業界トップクラスとの評価を得ています。
タレックスでは「認定プロショップ」という独自の制度を導入しています。
この制度により、販売店スタッフはタレックスから直接技術研修や接客指導を受けるため、高い技術力と信頼性が保証されています。
なお、タレックス製のサングラスは通販での購入ができません。
公式オンラインショップや釣具店での取り扱いはありますが、品質確認のためには店舗での直接購入が推奨されています。
このように、TALEXは高品質な製品づくりと丁寧な顧客サービスを通じ、多くの人々から厚い信頼を得ている偏光レンズメーカーです。
コンベックス
「コンベックス」は、一般的にはあまり知られていませんが、偏光レンズに詳しい人たちの間では非常に評価の高いメーカーです。
その最大の特徴は「明るい偏光レンズ」にあり、この特徴が釣り業界大手の「SHIMANO」にも認められ、一部製品に採用された実績を持っています。
特に人気が高いのは「シューターグリーン」というカラーで、独特な色合いと性能に熱烈なファンがいます。
このレンズは「偏光サングラスを使うと視界が暗くなりがち」と感じる方に特におすすめです。
コンベックスの主力商品である「PolaWING SPX」シリーズには、自社独自の染色技術が活用されており、偏光度99%、可視光線透過率38%という高性能を実現しています。
このシリーズには2種類の素材が用意されており、標準モデルの「SPX150」には「CR-39」が、度付きにも対応する高品質なモデルの「SPX160」には「MR素材」が使用されています。
特に「SPX160」は、もともと度付きレンズ用に開発された素材で、品質や性能の高さに定評があります。
予算に余裕がある方には、この「SPX160」を強くおすすめします。
まとめると、「コンベックス」は偏光レンズの品質と技術力に定評があり、明るさと高い偏光度を求めるユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
伊藤光学
伊藤光学は、業界を代表するメガネレンズメーカーの一つです。
その高い評価を支えるのは、優れたコーティング技術です。
この技術は偏光レンズにも応用され、光の反射や乱反射を効果的に抑え、クリアで快適な視界を提供しています。
伊藤光学は「RARTS」という新ブランドを立ち上げました。
当初は釣り専用の偏光レンズブランドとしてスタートしましたが、高い品質と幅広い用途への対応力から、現在では様々なシーンでの利用が広がっています。
RARTSの特徴として特に注目されるのが、優れたコストパフォーマンスです。
他社製品と比較してリーズナブルな価格設定でありながら、屈折率や加工性に優れたMR素材を使用し、品質の高いコーティング技術が施されています。
伊藤光学は、確かな技術力と品質へのこだわりに加え、コストパフォーマンスにも優れたRARTSブランドを通じて、偏光レンズ市場で独自のポジションを築いています。
偏光レンズメーカーを選ぶ時に比較するポイント
レンズ素材で比較する
偏光レンズを選ぶ際の重要なポイントの一つに、「レンズの素材」があります。
ここでは、主なプラスチックレンズの種類と、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。
CR-39
CR-39は、1940年代にアメリカで開発されたプラスチックレンズ素材です。
コストパフォーマンスが高く、色収差が少ないため、手頃な価格でクリアな視界を求める方に向いています。
ただし、耐久性や加工のしやすさにはやや課題があるため、長期間の使用や特殊加工を希望する場合は不向きといえます。
MRシリーズ
MRシリーズは、1987年に日本の三井化学によって開発された高性能なレンズ素材です。
特徴として、耐久性が高く加工が容易であること、薄型のレンズを作れるためデザイン性の高いフレームや高度な視力矯正にも対応できることが挙げられます。
一方で、性能の高さが価格に反映されており、比較的高価です。
その他のプラスチックレンズ
他にも、NXT、ポリカーボネート、トリアセテート、アクリルなど、多様な素材があります。
これらは目的や用途に応じて選ぶことが重要です。
例えばポリカーボネートは衝撃に強いため、スポーツやアクティブなシーンで使用する場合に最適です。
偏光フィルター素材で比較する
偏光レンズを選ぶ際には、使用されている偏光フィルター(偏光膜)の素材とその特性を理解することが大切です。
代表的な偏光フィルターには「ヨード系(ヨウ素系)フィルター」と「染料系フィルター」の2種類があります。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
ヨード系(ヨウ素系)フィルター
明るく鮮明な視界
他の偏光フィルターと比較して視界が明るく、はっきりとした見え方が特徴です。
耐久性が低い
長期間の使用や紫外線の影響を受けやすく、時間とともに劣化が進みます。
水に弱い
湿気や雨など水分の影響で性能が落ちることがあります。
染料系フィルター
耐久性が高い
ヨード系と比べて劣化しにくく、長く安定した性能を保ちます。
熱・水に強い
高温や水分の影響を受けにくく、さまざまな環境で安定して使用できます。
明るさはやや劣る
ヨード系フィルターに比べると少し暗めで、視界の明瞭さはやや劣ります。
レンズ製法で比較する
偏光レンズを選ぶ際には、レンズの製法によって性能や価格が大きく変わります。
ここでは主な製法を比較し、それぞれのメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
ワンブロック成型
偏光フィルムとレンズ素材を一体化し、ひとつのブロックとして製造する方法です。
強度や耐久性に優れ、品質面では非常に信頼性が高いのが特徴です。
ただし、製造に高度な技術が必要なため、価格が比較的高くなる傾向があります。
貼り合わせ成型
偏光フィルムとレンズ素材を接着剤で貼り合わせる製法です。
ワンブロック成型よりも製造コストが抑えられるため、価格面でのメリットがありますが、接着面が劣化したり剥がれたりするリスクがあります。
フィルム貼り
既製のレンズ表面に偏光フィルムを貼る最も簡易な製法です。
コストをさらに低く抑えられる一方で、フィルムが剥がれやすく傷つきやすいというデメリットがあります。
これらの製法ごとの特徴を理解し、自分の用途や予算に最適な偏光レンズを選びましょう。
偏光レンズメーカーを比較 各メーカーの違いと選び方・まとめ
偏光レンズはメーカーごとにさまざまな特徴があります。
ご自身の予算や使用目的、求める品質に応じて、最適なレンズを選ぶことが大切です。
あなたにぴったりの偏光レンズメーカーが見つかりますよう願っております。
関連記事

Land&rutoで取り扱っているカラーレンズのメリットとデメリットの紹介ページです。
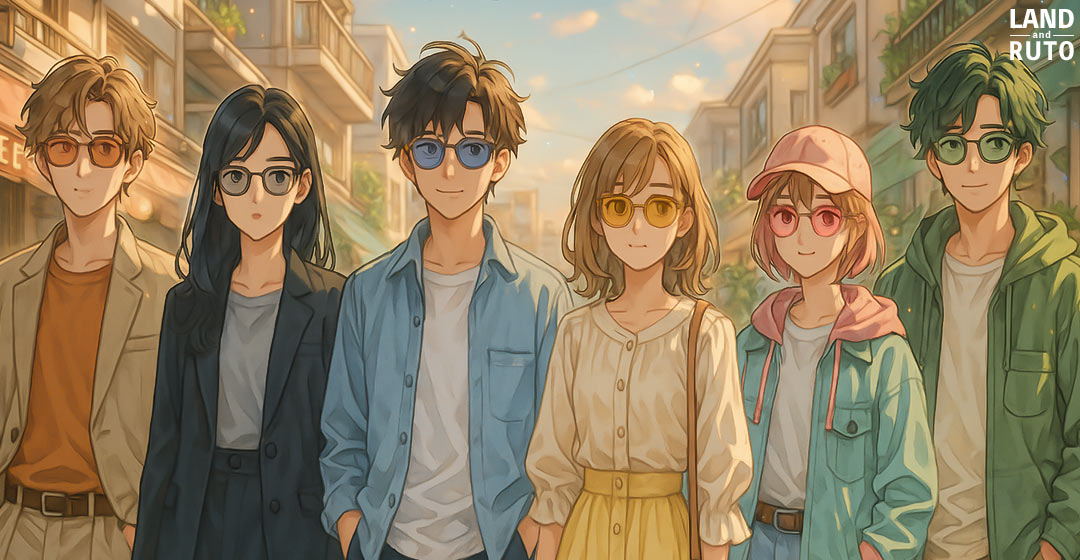
カラーレンズは色の種類やレンズ濃度によって使用感や相手に与える印象を変わります。カラーレンズは使用用途に合わせてカラーやレンズ濃度を選ぶことによって、お困りごとを解決することができるアイテムです。

偏光レンズは屋外アクティビティや日常生活で視界をクリアにし、目の疲れを軽減します。特にアウトドアやスポーツでの使用がおすすめですが、水や高温には弱いというデメリットに注意が必要です。

本当に偏光レンズが使われているのか確かめたい時に便利な偏光レンズかどうかを見分ける方法は様々あります。身近にあるガラスの映り込みや偏光フィルターを使って偏光レンズか見分けることができます。

サングラスを選ぶ際は、デザインだけでなく、レンズの機能や用途を考慮することが重要です。調光レンズは光の強さに応じて色が変わり、偏光レンズは反射光をカットする機能があります。

運転時の適切な視界は安全の基本で、特に晴天や反射光が強い時にはサングラスが不可欠です。太陽光や反射光は事故リスクを増加させ、偏光サングラスはこれをカットして視認性を向上させます。

調光レンズには様々なデメリットがありますが、使用用途やシーンが合っていれば、メガネとサングラスを掛け変えることなく使うことができる眼鏡です。

調光レンズの寿命は約2〜4年で、2〜3年経つと効果が薄れるため、3年を目安に交換を検討すべきです。
店舗情報

Land&ruto
・〒 921-8133 石川県金沢市四十万町イ152
・☎ 076-208-3312
・営業時間 9:30~19:00
・完全予約営業 不定休
金沢駅からLand&rutoへのアクセス
- 鉄道をご利用の場合
-
金沢駅~西金沢駅
IRいしかわ鉄道線 約3分西金沢駅~新西金沢駅
徒歩約2分新西金沢駅~四十万駅
北陸鉄道石川線 約15分四十万駅からLand&rutoまで徒歩約8分
- マイカーをご利用の場合
-
金沢駅からLand&rutoまで約20分
金沢駅へのアクセス
東京・名古屋・大阪・3大都市圏からいずれも約2時間30分
Land&ruto店長

Land&ruto店長 北上寿一
石川県金沢市の完全予約制の眼鏡店 Land&rutoでメガネを販売しています。
メガネ専門店、大手チェーン店、コンタクトレンズ販売店を経て2005年開業。時代の流れに合わせて変化するメガネのニーズに対応するため日々努力しています。眼鏡作製技能検定 1級眼鏡作製技能士
運営会社情報
| 運営会社 | 有限会社北上 |
| 住所 | 石川県金沢市四十万町イ152 |
| 郵便番号 | 〒921-8133 |
| 電話番号 | 076-208-3312 |



